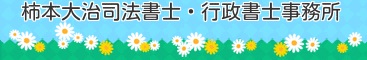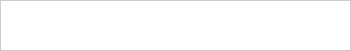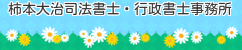遺言
遺言(いごん)
一般的に、遺言(ゆいごん)と言われていますが、法律上は、遺言(いごん)と読みます。
最近では、エンディングノートという言葉も耳にしますが、エンディングノートは、遺言と異なり、法的な効力を有する文書ではありません。
会社経営に遺言を活用する場合もあります。
遺言は会社の事業承継に有効な方法のひとつでもあります。
公正証書遺言や、家庭裁判所で検認手続を受けた自筆証書遺言などがあれば、その遺言にしたがって相続手続を行うことができます。
遺言書を残しておけば、相続手続がスムーズに行われ、相続に関するトラブルを防止することができます。
遺言がある場合とない場合ではどう違う?
相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。
例えば、亡くなったAさん(被相続人)には、子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とAさんの兄弟が相続することになりました。
兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも達することがわかりました。
→遺留分
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。
遺言された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、遺言書の作成のサポート業務を行っております。
正しい遺言書を残しましょう!
将来のトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ書いておきたい遺言書。
ただし、たとえ夫婦でも、同一の書面に夫婦二人で一緒に遺言をすると無効になります。
遺言書の種類
主に利用されている遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
以下に2つの遺言の違いを説明します。
自筆証書遺言や公正証書遺言の他には、秘密証書遺言などもあります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自署し、押印して作成。 ※自筆証書遺言の方式緩和 自筆証書遺言の財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(2019年1月13日施行) | 遺言者が、原則として、証人(2人以上)と共に公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。 |
| メリット | ◆遺言者が単独で作成できる。 ◆費用がかからない。 ※法務局における自筆証書遺言書保管制度による場合は手数料が必要です。 | ◆遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。 ◆原本は、公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。 ◆家庭裁判所による検認手続きが不要。 |
| デメリット | ◆遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、意味不明、形式不備等により遺言が無効になるおそれがある。 ◆自己または他人による紛失(失念)・滅失・隠匿・偽造・変造のおそれがある。 ◆遺言者亡き後、家庭裁判所の検認手続きが必要。 ※法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管されている遺言書の場合は、検認手続き不要 | ◆証人(2人以上)を選ぶ必要があるが、受遺者及びその配偶者、推定相続人等は証人になれない。 ◆手数料を必要とする。 |
民法(相続法)改正~自筆証書遺言の方式緩和~
自筆証書遺言の財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(2019年1月13日施行)
遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言どっちがいい?
自筆証書遺言は手軽に作成できます(費用がかからない)が、相続が発生した後に、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。
公正証書遺言は、偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。
また公正証書遺言は、後に家庭裁判所での検認手続きが不要となり、遺言中で遺言執行者を定めておけば、不動産の名義変更にも便利な方法です。
公正証書遺言は、公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。
遺言でできること
相続分の指定
誰にどの割合で相続させるかを指定できます。
民法の法定相続分を変更できます。
→遺留分
認知
婚姻届を出していない男女間に生まれた子を、親が戸籍上の手続きによって自分の子だと認めることです。
遺言によって認知されてもその子は相続人になれます。
遺贈や寄付による財産処分
遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付できます。
後見人と後見監督人の指定
相続人の廃除や廃除の取り消し
遺産分割方法の指定またはその委託
相続人相互の担保責任の指定
遺言執行者の指定または指定の委託
遺留分減殺方法の指定など
→遺留分
遺言書Q&A
Q 自筆証書遺言につき、自筆で書くのが面倒なので、ワープロ・パソコンやビデオ録画をしたもので作ってもよいですか?
A ワープロ、パソコン等で作成されたもの、ビデオで収録したものなどは法的な意味での効力がありません。
すべて自署する必要があります。
※自筆証書遺言の財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(2019年1月13日施行)
Q 遺言の内容を人にみられたくない・・・でも誰かにきちんと保管してもらいたい、そんな遺言はないですか?
A 秘密証書遺言という方法があります。
遺言者が遺言を作成したうえで署名押印をし、その後封書で閉じ、封印(遺言書で使用した印鑑を使用)をして公証人に提出します。
その際、遺言者は自分の遺言書であることと、住所氏名を公証人に申述します。公証人はその申述と日付を封書に記載して、遺言者と証人(2名以上)がともに署名、押印するものです。遺言自体は自署による必要がありません。
秘密証書遺言は、特殊な場合に使うものと考えてよいと思います。また、比較的自由に封筒の中にものを入れられるということから利用する場合もあります。
その他、特別な方法として危急時遺言など特別方式の遺言についても法律(民法)には規定されています。
遺言書の内容等については、次のようなことに配慮する必要があります。
◆税務面を考慮すること(税務面については、税理士や税務署にご相談して下さい。)
◆民法上の遺留分などを検討すること
→遺留分
◆遺言の内容が実現可能なこと
など
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所
 →取扱業務
→取扱業務